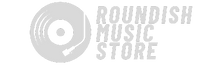大学生の頃、夜な夜な通っていたのは京都のクラブ「METRO」だった。
あの駅からの階段を降りていくと、湿った空気と煙草の匂い。
そこに鳴っていたのは、大音量のジャズやブラジル音楽だった。
その日はCOOL TO KOOLである。
KYOTO JAZZ MASSIVEとMONDO GROSSOが入り乱れるパーティだ。
耳をつんざくほどのサウンドなのに、なぜか心はどんどん軽くなる。
まだ若干20歳の僕にとってはフロアは恐ろしい大人の集まりに見え、
バーカウンターのそばでそっと熱気を感じていた。
そして思った。
「このレコード、どこで手に入るんだろう?」
知ってるレコード屋をいくら回っても、あのDJブースから流れてくる音は見つからなかった。
もしかして、あの人たちしか持ってないんじゃないか?
いや、きっとそうだ。
だったら、もっと上をのぞいてみたい。
頭に浮かんだのはロンドンのDJ、Gilles Peterson。
雑誌で見かけていた人で、名前の響きだけでもう特別に聞こえる。
「彼と友達になったら、めちゃ良いレコードザクザクやん」
そんな稚拙な思いが頭の中をよぎった。
そう思ったら、もういても立ってもいられなかった。
夏の暑い日、大学の事務室に行って退学届を出す。
ペンを走らせながら「ほんとにこれでいいのか?」なんて一瞬よぎったけど、すぐに「まぁなんとかなるだろ」と自分に言い聞かせた。
その足で旅行代理店に直行して、チケットを予約。行き先はロンドン。片道切符。
(ビザが切れるまでは帰ってくるつもりなんてさらさらなかった。)
できて間もない関西空港から飛行機に乗り込むと、胸の奥で妙な高揚感が広がった。
雲の上から見える夕焼けがやけに特別に思えて、「これが新しい人生の幕開けか」なんて、ちょっと映画っぽいことを考えていた。
やっと降り立ったロンドンは、思っていたよりも乾いた風が吹いていた。
湿気に慣れた身体にはその風が新鮮で、鼻の奥がツンとする。
「これがロンドンの匂いか」なんて、柄にもなく思った。
それは排気ガスと雨上がりの石畳の匂いが混ざったものだったけれど、あのときの僕にはそれがまるで夢の香りに感じられた。
この街で、僕のレコード人生が始まるなんて、そのときはまだ知る由もなかった。