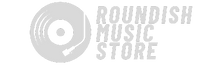ジャズと聞くと、タバコの煙がゆらめくクラブで、黒光りするトランペットが静かに鳴っている──そんな絵を思い浮かべる人も多いだろう。けれど90年代、ターンテーブルの上で回るレコードが、もう一度ジャズを光らせた瞬間があった。
ジャズとDJ。見た目はまるで違うけれど、ふたりの共通点は「即興」。ステージで音を紡ぎ続けるジャズマンと、フロアの空気を読み取って瞬時に曲を繋ぐDJ。結局のところ、どちらも「自由」の旗を掲げていたのだ。
そうして生まれたのが“アシッド・ジャズ”。ジャミロクワイやインコグニートが代表格で、ファンクやソウルの熱気にジャズのグルーヴをブレンドし、クラブのダンスフロアを揺らした。サックスとスクラッチ、スウィングとドラムマシン。ちぐはぐなようでいて、妙にハマる。その化学反応は魔法みたいだった。
当時のフロアは、スーツ姿じゃなくてストリートファッションに身を包んだ若者であふれていた。彼らは「これってジャズなの?」と首をかしげながらも、体を揺らすことをやめなかった。ジャズは“難しい音楽”の殻を脱ぎ捨てて、“楽しむ音楽”として生まれ変わったのだ。
もしルイ・アームストロングが生きていたら? きっと目を丸くして「最高だね、若い世代が楽しんでる」と笑っただろう。チャーリー・パーカーなら「俺のサックスをもっとミックスしろ!」とDJブースに飛び込んでいたかもしれない。
もちろん、この物語にはちょっとした真面目なメッセージもある。音楽は時代やジャンルを飛び越えて生き続ける──ということ。90年代にジャズとDJが出会ったことで、ジャズはただの“歴史的遺産”じゃなく、今を生きる音楽として蘇った。ローファイ・ヒップホップやエレクトロスウィングにまで影響を与えているのは、その証拠だ。
90年代のクラブカルチャーは、音楽的自由と冒険心の黄金期だった。もし今、ダンスフロアでスウィングしながら「これもジャズの子孫なのか」と思ったら──その瞬間、あなたもこの長い物語の続きを生きているのかもしれない。