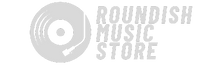Joe Davis の車に乗り込んだ瞬間、胸の鼓動がワンテンポ早くなる。
日本ではDJの知り合いなんて片手で数えるほどしかいないのに、
気づけばロンドンで、著名DJ・プロデューサーの車に揺られている自分がいる。
「これは来てよかった…いや、来るしかなかった!」
そう心の中で念仏のように唱える。
昭和のサラリーマンばりの “足で稼ぐ精神” が、ここロンドンで通用するとは思わなかった。
車はしばらく街を走り、ブーンと静かに停まった。
「ここが事務所だぜ」
Joe が軽く言う。
目の前にあるのは、意外にも普通の建物。
もっと奇抜で、巨大なポスターやレコードが貼られているような所を想像していたが、
拍子抜けするほど静かで、生活感すら感じる場所だった。
妙な緊張が少しほどける。
「カミーヤさん、ちょっと入って待っといて」
案内された部屋には数人が作業していた。
一人は書類の山と格闘し、もう一人はキーボードをぽつぽつ鳴らしてる。
その奥では、Joe がひっきりなしに誰かと電話をしている。
でもその“ひっきりなし”が、ひっきりなし過ぎる。
全然終わらない。
待てど暮らせど終わらない。
「これが海外のルーズさか…」
昭和サラリーマンタイムとはかけ離れた“Far Outタイム”を、19歳はイスの上で味わう。
ようやく電話が終わり、Joe がこちらへ向き直った。
「次のコンピレーションの話をしてたんだ。
誰と電話してたと思う?」
試されてる気がして、とりあえず音楽好きが言いがちな名前を出す。
「ジャイルス・ピーターソンとか?」
Joe は首を振って笑った。
「No, no… Marcos Valle だぜ」
え?
ええ!!?
あのブラジル音楽の重鎮、マルコス・ヴァーリ!?
“CRICKET SONG”の!?
一瞬、視界の端がスローモーションになった気がした。
日常とはまったく別ベクトルの出来事が、僕のまわりで渦巻いている。
ロンドンに来て2週間足らず、19歳の脳みそは完全にキャパオーバー寸前だ。
でも——
この“ありえない世界”に巻き込まれていく感覚が、たまらなく心地いい。